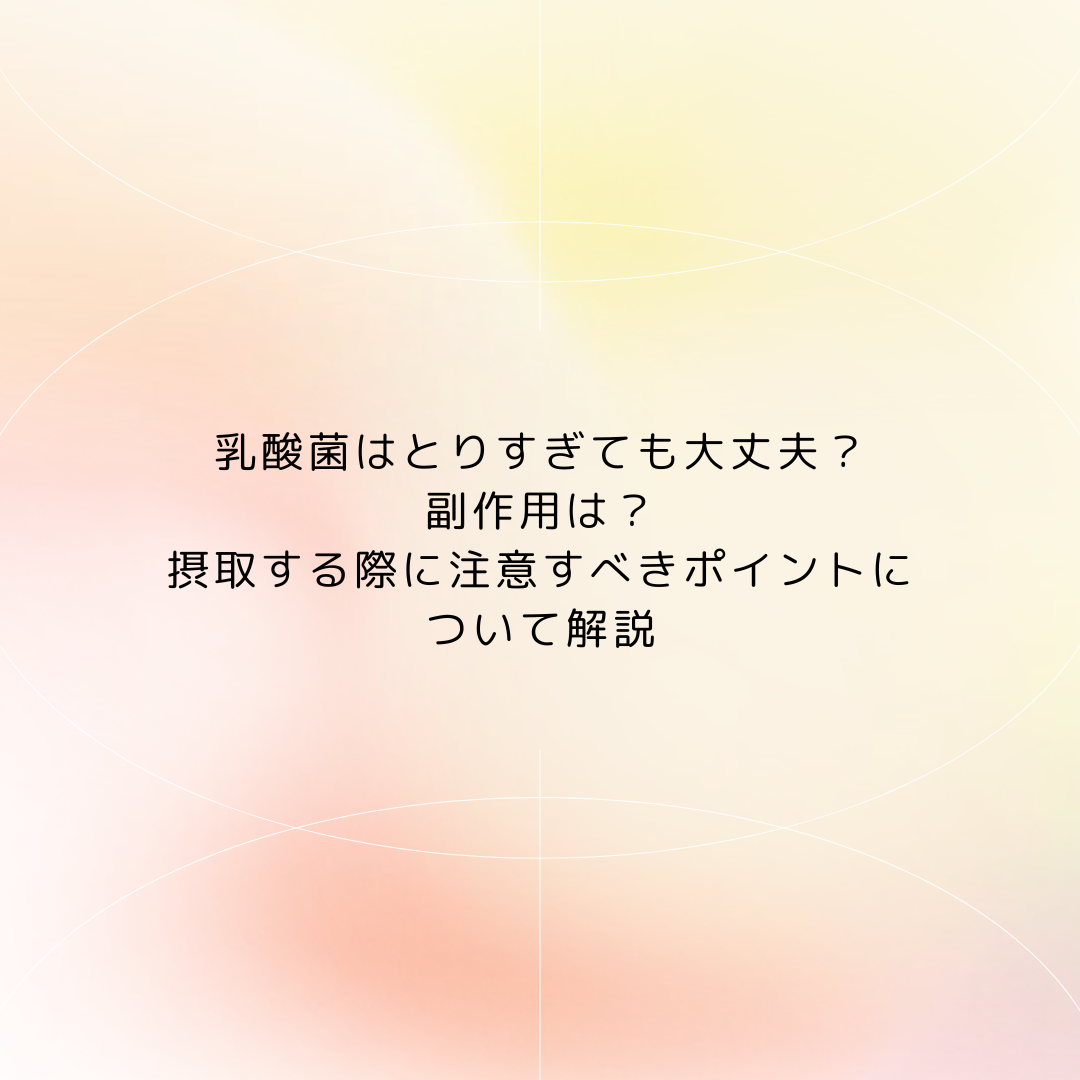
乳酸菌はとりすぎても大丈夫?副作用は?摂取する際に注意すべきポイントについて解説
ヨーグルトやサプリなどで身近な乳酸菌は、腸内に存在する微生物として注目されています。腸をサポートすることによって毎日の調子を守る成分として、日々の生活に取り入れたいと考えている人は少なくありません。
しかし、「毎日摂取しても大丈夫なのか?」「多めに摂った方が良いのではないか?」と気になっている方も多いのではないでしょうか?
実は、乳酸菌は多くとれば良いというものではありません。体調や体質、乳酸菌が含まれている食品によっては、とりすぎることによって、さまざまな影響が出てしまう場合があるのです。
そこで、この記事では、乳酸菌を安全にとるための方法を解説します。乳酸菌の基本的な働きから、とりすぎによる影響、適切とされる摂取量や摂取時の注意、体調不良時の対処法など、無理なく乳酸菌をとり続けるための工夫について紹介します。
乳酸菌とは?基本的な働きについて

乳酸菌は、私たちの体内で暮らす微生物のひとつです。腸内環境などに関わる存在として注目されており、その名前は多くの人に知られています。
まず、乳酸菌が実際にどのような働きをしているのかを見てみましょう。
乳酸菌の分類と主な特徴
乳酸菌には様々な種類があり、代表的なものにはラクトバチルス属やエンテロコッカス属などがあります。
これらの微生物は形状によっても分類され、球状のもの(球菌)や棒状のもの(桿菌)に分けられています。それぞれに異なる特徴があり、体内での働き方や生息場所が少しずつ違っているのが通常です。
|
菌の種類 |
主な特徴 |
代表的な効果 |
主な生息場所 |
|
ラクトバチルス属 |
棒状 |
腸内環境をサポートする |
小腸・膣 |
|
エンテロコッカス属 |
球状 |
腸内環境をサポートする |
大腸 |
|
ビフィズス菌 |
Y字型 |
善玉菌として働く |
大腸 |
|
ストレプトコッカス属 |
連なった球状 |
消化に関わる働き |
口腔・腸管 |
ビフィズス菌は腸内の「善玉菌」として知られていますが、厳密には乳酸菌とは別のグループに属しています。ただし、腸内環境を整えるという点で、乳酸菌と共通して語られることが多い微生物です。
体内での役割と注目される点
乳酸菌は腸内で「善玉菌」の一員として存在し、腸内フローラ(腸内細菌のバランス)に関わるとされています。そのため、腸内環境を健やかに保つサポートが期待されており、便通や栄養の吸収を助ける働きなど、体調全般への関わりが注目されています。
近年は「腸と脳のつながり」に関する研究も進んでおり、腸内環境と気分やストレスの関係も注目されています。また、乳酸菌の活動が体の中の不要な物質の排出を助ける可能性についても研究が進められています。
このような研究により、乳酸菌は心身の健康を考えるうえで役立つ存在として、関心を集めているのです。
乳酸菌のとりすぎには副作用がある?

乳酸菌は身近で取り入れやすい成分として人気がありますが、たくさんとれば良いというものではありません。「体に良さそうだから」と多めに摂取すると、人によっては思わぬ体調の変化に繋がることがあります。
一般的に見られやすい体の変化
乳酸菌を一度に多くとると、腸内環境が急激に変化します。そのため、体がその変化に慣れるまでは、一時的に不快感を覚えることがあります。
特に、乳酸菌が含まれている食品の多くは、乳製品や発酵食品です。乳酸菌をとりたいからといって、これらを多く摂取すると、乳酸菌そのものによる影響だけでなく、食品の成分による影響から、不快感を覚える可能性があります。
よく知られているのは消化器系の変化で、お腹がゆるくなったり、張りやすくなったりするケースです。こうした反応には個人差があり、乳酸菌の種類や量、また体質や腸内環境の状態によって、程度が異なるのが通常です。
消化器に現れやすい不快感
乳酸菌の過剰摂取による最も一般的な不快感は、消化器系の症状だとされています。
・下痢:排便の回数が増えることがある
・腹部の違和感:お腹が痛んだり重く感じる場合がある
・お腹の張り:ガスがが溜まりやすくなることがある
・胃のもたれ:消化に時間がかかるように感じることがある
乳酸菌が腸内で急激に増えると、腸の動きが活発になります。そのため、排便や消化に関わるお腹の不調に繋がる可能性があります。
また、乳糖不耐症の人は、乳製品に含まれる乳糖を分解できず、お腹に不快感を覚えやすくなります。さらに、発酵食品に含まれる食物繊維や発酵過程の副産物によってガスが出やすくなることも。
多くの場合、これらの不調は摂取量を減らすことで和らぐとされています。
不快感の有無は体調や免疫とも関わっている?
乳酸菌は体の健康を考えるうえで注目されていますが、たくさんとれば良いというわけではありません。
特に体調が不安定な方や、アレルギー・持病がある場合は、摂取量が多すぎることで体の反応が強く出ることも考えられます。特に免疫力が低下している時は注意が必要です。気になる症状がある場合は、自己判断せずに必ず専門家に相談しましょう。
体質や体調に合わせて無理なく続けられるよう、量やタイミングを調整しながら、自分に合ったとり方を見つけることが大切です。
乳酸菌の適切な摂取量とおすすめの頻度
乳酸菌を安心して取り入れるためには、自分に合った摂取量や頻度を理解しておくことが大切です。「たくさんとれば体に良い」というものではなく、体調や体質に応じた適切な量を、食事や生活に無理なく取り入れられる範囲で、継続して摂取することがポイントです。
1日の目安量
乳酸菌の摂取量には明確な基準はありませんが、食品やサプリメントでは「数億~数百億個程度」が目安とされていることが多いです。
1日の摂取量はヨーグルトの場合は1日100~200g程度が一般的な量で、市販のカップ1個分にあたります。また、乳酸菌飲料は1本、乳酸菌の数は数億~数十億個程度が目安となります。ただし、どちらも、糖分やカロリーに注意して選ぶことが大切です。
発酵食品に含まれる乳酸菌は食品ごとに異なります。納豆や漬物などに含まれる乳酸菌は、製造方法や保存状態で変動が大きいため、「何億個」とは断言しづらいです。そのため、塩分や糖分などの栄養バランスを考えながら、食事の一部として適量を、日常的に取り入れると良いでしょう。
サプリメントを利用する場合は、1日数十億~数百億個の範囲で摂取するのが一般的ですが、必ず製品に記載されている用法・用量を守ることが大切です。自己判断で量を増やすのではなく、メーカーごとの案内を参考にすることが、安全な摂取につながります。
継続してとることの大切さ
腸内の乳酸菌は常に入れ替わり、体内にずっと定着するわけではありません。摂取をやめると数日~1週間で減ってしまうこともあるため、毎日継続してとることが何より大切です。一度に多くとるよりも、少量を毎日習慣化することを心がけましょう。
朝食にヨーグルトを加える、夕食後にサプリメントを利用するなど、決まった時間にとる習慣を作り、生活リズムに合わせることで、摂取し続けやすくなります。
ただし、変化を実感するまでには個人差があります。数日で感じる人もいれば、数週間から1ヶ月程度かけてゆっくりと体調の違いを意識できる人もいるため、焦らず長期的な視点で取り入れることが大切です。
手軽に乳酸菌を1兆個とれる!!
乳酸菌摂取時に注意が必要な人とは?
乳酸菌は多くの人にとって身近で取り入れやすいものですが、体調や現在受けている治療の内容によっては注意が必要な場合もあります。
・免疫機能が低下している人
・慢性的な疾患がある人
・薬を服用している人
・高齢の人
免疫力が低下している人は乳酸菌を含む食品でも体調に影響が出ることがあります。また、持病がある方は、乳酸菌の摂取が体への負担となる場合もあるでしょう。薬を服用している場合、乳酸菌が薬の働きに影響を与えてしまうことも。
このような場合は、乳酸菌を摂取する前に必ず医療専門家に相談することが大切です。医師や薬剤師へ相談することをおすすめします。
さらに、高齢の場合、消化機能が緩やかになっている場合があります。影響が強く出やすいことがあるため、少量からの摂取が望ましいでしょう。
乳酸菌を含む食品と摂取方法のポイント

毎日の食事に乳酸菌を取り入れる際は、食品の特徴やとり方を理解しておくことが大切です。市場には様々な乳酸菌入りの食品が並んでおり、それぞれに異なる特徴があります。
そのため、自分のライフスタイルに合った選び方を意識するのがおすすめです。
ヨーグルトや発酵食品の選び方
ヨーグルトを選ぶ時は、生きた乳酸菌が含まれているかどうかを確認しましょう。商品パッケージに「生きた乳酸菌」や「プロバイオティクス」の表示があるものを選ぶのがおすすめです。
また、チーズ、キムチ、納豆、味噌といった発酵食品を日々の食事に取り入れるのも良いでしょう。日本人の食卓に馴染みがあり、自然に乳酸菌を取り入れられる身近な食品です。
乳酸菌飲料は手軽にとれるところが魅力ですが、糖分の多い商品もあるため、無糖や低糖タイプを選ぶとより安心でしょう。
|
食品の種類 |
特徴 |
注意点 |
おすすめ度 |
|
プレーンヨーグルト |
生きた菌が含まれるものが多い |
砂糖の添加に注意 |
★★★★★ |
|
発酵チーズ |
保存性が高い |
塩分や糖質がやや高め |
★★★★☆ |
|
乳酸菌飲料 |
手軽に取り入れられる |
甘味料や糖分に注意 |
★★★☆☆ |
|
納豆・味噌 |
日本の伝統食品 |
塩分量の確認が必要 |
★★★★☆ |
サプリメントとの使い分け
食品からの乳酸菌摂取とサプリメントには、それぞれ独自のメリットがあります。
食品からの摂取は自然で安全性が高く、乳酸菌に加えて他の栄養素も一緒にとれるのが魅力です。一方サプリメントは、菌の種類や数を確認しやすく、忙しい方でも続けやすいのが利点と言えるでしょう。
忙しい生活を送る人にとってサプリメントは便利な選択肢となりますが、それだけに偏ると、その他の栄養素の摂取をおろそかにしてしまいがちです。そのため、バランスの取れた食事と組み合わせながら、ライフスタイルに合った摂取方法を選ぶことを心がけましょう。
乳酸菌摂取後の不快感や違和感への対処法
乳酸菌を取り入れた後に、お腹の張りや違和感を覚えることがあります。多くの場合は一時的なものとされていますが、気になる場合は以下のような方法を試してみましょう。
体調の変化を感じたら、まずは落ち着いて状況を把握し、適切に対処することで、安心して乳酸菌をとり続けやすくなります。
軽い不快感があるとき
お腹の張りや軽い不快感を感じた場合は、摂取量を一時的に減らすことから始めましょう。通常の半分程度に調整して様子を見てください。
水分補給を心がけることも大切です。十分な水分は消化をサポートしてくれます。また、食事のバランスを見直し、食物繊維の多い食品と一緒に摂取することで、腸内での働きがスムーズになることも。
症状が軽微であれば、2〜3日様子を見ながら徐々に摂取量を戻していきましょう。
医師や専門家に相談した方がよい場合
以下の症状が現れた場合は、すぐに医師に相談することをおすすめします。
・数日たっても症状が改善しない
・下痢や強い腹痛、発熱などのはっきりした不調がある
・発疹や呼吸のしづらさなど、アレルギーの可能性がある症状が出ている
このような時は自己判断せず、医師や薬剤師などの専門家に相談することが大切です。特に免疫力が低下している場合や持病をお持ちの方は、軽微な症状でも早めに医師に相談しましょう。
安全に乳酸菌の取り入れるためのポイント
乳酸菌を生活に取り入れる方法はひとつではありません。食品やサプリメントを上手に活用し、自分に合った続け方を見つけることが大切です。
ここからは、ライフスタイルの一部として乳酸菌を取り入れる際に意識したいポイントをご紹介します。
バランスの良い食事との組み合わせ
乳酸菌は単独でとるよりも、他の栄養素と組み合わせることで、毎日の食事に自然に馴染みやすくなります。ヨーグルトやサプリメントなどから乳酸菌を摂取するだけでなく、日々の食事との組み合わせを意識してみましょう。
【組み合わせたい食品の例】
・食物繊維が豊富な野菜や果物 :ごぼう、にんじん、キャベツ、りんご、バナナなど
・オリゴ糖を含む食品 - バナナ、玉ねぎ、にんにくなど
・発酵食品の組み合わせ - 味噌、納豆、キムチなどを一緒に摂取
例えば、食物繊維を含む野菜や果物は乳酸菌が腸に定着する働きを助けます。また、乳酸菌やビフィズス菌の栄養源として利用されるオリゴ糖を含む食品を一緒にとるのも良いでしょう。さらに、発酵食品を組み合わせて摂取することで、食品ごとに顔ぶれの違う微生物や発酵由来の成分を取り入れられるほか、日々の食事に組み込みやすくなるでしょう。
個人の体質に合わせた摂取方法
人によって体質や生活習慣は異なります。そのため、それぞれのライフスタイルに合わせて工夫しながら乳酸菌を取り入れてみましょう。
【体質に合わせた摂取のポイント】
・はじめは少量から試してみる:推奨量の半分程度から開始
・体調の変化をしばらく観察する:2週間程度様子を見ながら調整
・いくつかの種類を試す:自分に合う乳酸菌株を見つける
・摂取する時間帯を変えてみる:朝食後、夕食後など最適なタイミングを探す
お腹が敏感な方は、ヨーグルトよりもサプリメントの方が適している場合もあります。個人の体質を理解して、無理のない方法を選択することが大切です。
長く続けるための工夫
乳酸菌は、一度に大量にとるよりも、習慣として少しずつとり続けることが大切です。
【長く続けるためのポイント】
・習慣化しやすい時間を決める:毎日同じ時間に摂取する
・複数の摂取源を用意する:ヨーグルト、サプリメント、発酵食品を使い分ける
・無理のない量を維持:継続できる適量を見つける
・定期的な見直し:数か月ごとに評価しながら体調に合った方法を探していく
健康維持の観点からも、乳酸菌摂取は生活の一部として自然に取り入れることが理想的です。短期間では変化を感じにくいことがあるため、持続可能な方法を見つけることが成功の鍵になるでしょう。
手軽に乳酸菌を1兆個とれる!!
乳酸菌はとりすぎても大丈夫?副作用は?摂取する際に注意すべきポイントについて解説 のまとめ
乳酸菌を摂取する方法は、ヨーグルトや発酵食品、サプリメントなど、幅広い選択肢があります。大切なのは「大量にとること」ではなく「自分の体に合った方法で無理なく続けること」です。摂取量の目安や注意点を意識しながら、自分の体調に合った方法を見つけることを心がけましょう。
毎日の食事にちょっとした工夫を加えて乳酸菌を気軽に取り入れることで、食生活がより楽しくなったり、腸内環境を意識する習慣がついたりと、心と体の両面で前向きな変化を感じやすくなります。自分に合った方法を探しながら、気軽に楽しく習慣にしていくことで、心と体をやさしく整える第一歩を踏み出せるでしょう。

