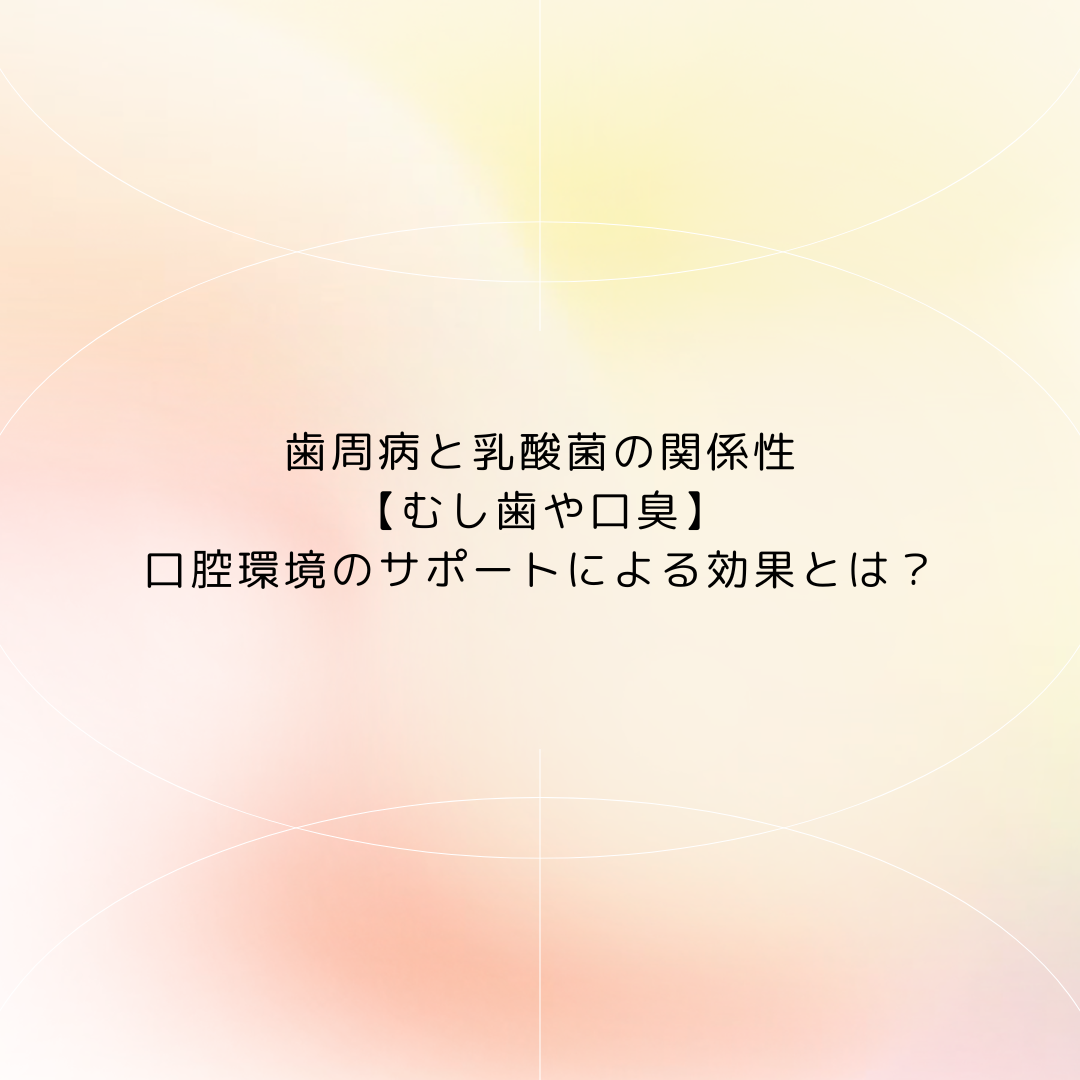
歯周病と乳酸菌の関係性【むし歯や口臭】口腔環境のサポートによる効果とは?
「最近、歯ぐきが下がってきたかも」
「口のニオイが気になるけれど、もしかして歯周病?」
毎日歯磨きをしているにも関わらず、このような心配を感じていませんか?
歯周病は、気づかないうちに進行し、最悪の場合は歯を失うこともある怖い病気です。口腔内環境を整えるためには、正しい歯磨きや定期的な歯科検診が大切ですが、実は、歯周病と乳酸菌の関係についても、研究が進められています。
近年の研究では、特定の乳酸菌が従来の歯磨きやうがいだけでは届かない部分にも働きかけ、口腔内の環境づくりをサポートするとされているのです。
そこで、この記事では、薬剤師監修のもと、歯周病と乳酸菌の関係について、むし歯や口臭との関わりや、口腔内環境をサポートする乳酸菌の種類、日常生活で実践できる具体的な方法まで詳しく解説します。
歯周病に関与する口腔内細菌と乳酸菌
口腔内には、私たちが想像しているよりも、はるかに多くの細菌が存在します。健康な人の場合、約300から500種類の細菌が口の中に生息しているのが通常です。
これらの細菌には善玉菌と悪玉菌が存在し、口腔環境に大きな影響を与えています。善玉菌と悪玉菌の適切なバランスが保たれれば、口の中の健康が維持されます。しかし、この2つの菌のバランスが崩れると、口腔内に問題が発生してしまうのです。
口腔内細菌バランスが歯周病に影響を与えている?
健康な口腔内では善玉菌が優勢です。善玉菌が良く働いていると、悪玉菌の増殖が自然に抑制されます。
しかし、食生活の乱れやストレス、口腔ケア不足によって細菌バランスが崩れると、悪玉菌が増殖しやすくなります。悪玉菌が増えると、歯茎の炎症や歯周ポケットの形成といった、歯周病の原因が作り出されてしまうのです。
歯周病の進行を防ぐためには、善玉菌が十分に存在し、悪玉菌の居場所を奪って、その増殖を防ぐといった細菌バランスを正常に保つことが重要です。そのため、細菌同士の競合関係を活用する手段として、乳酸菌の摂取が注目されているのです。
善玉菌と悪玉菌の口の中での働き
善玉菌は口腔内で様々な良い働きをしています。
善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を産生することで、悪玉菌が生息しにくい酸性環境を作り出します。また、限られた栄養源を善玉菌が優先的に利用することで、悪玉菌の活動を制限してくれます。
一方、悪玉菌は歯周病の原因となる毒素を産生します。特にジンジバリス菌などの歯周病菌は、歯茎の組織を破壊する酵素を分泌し、炎症を引き起こします。
これらの悪玉菌は、口腔内のpHが中性からアルカリ性に傾くと活発になります。そのため、善玉菌による酸性環境の維持が、口腔内環境にとって重要な意味を持つのです。
善玉菌を積極的に摂取することは、口腔内の細菌バランスを整え、口腔内環境の維持をサポートするとして期待されています。
歯周病と乳酸菌の関係がなぜ注目されるのか?
近年、歯周病と乳酸菌の関係が明らかになってきています。
乳酸菌は善玉菌の一種で、口腔内などの環境を良好に保つ働きをする微生物です。
乳酸菌の中には、歯周病菌やむし歯菌に対抗するものがあります。これらの乳酸菌は、歯周病の原因となる口腔内のトラブルを起こしにくくしたり、口腔内のpHを維持したりすることによって、口腔内の環境づくりをサポートすることが期待されています。
また、善玉菌である乳酸菌を摂取することで、善玉菌と悪玉菌のバランスが正常化されれば、善玉菌の働きが助けられ、体内の免疫の働きも整えやすくなります。その結果、健康な口腔内環境を維持しやすくなるとされているのです。
さらに、乳酸菌の継続的な摂取が関わる以下のような項目についての研究も進められています。
【研究で報告されている項目例】
-
歯周ポケットの深さ
-
歯茎の出血
-
歯茎の腫れ
-
口腔内の炎症マーカー
など
これらの口腔内環境の維持への寄与には個人差があり、すべての人に同じようなサポートが期待できるわけではありませんが、お口の健康維持の一環として、一部の乳酸菌の活用が注目されていると言えるでしょう。
乳酸菌によるむし歯・口臭に関わる口腔環境の維持について
乳酸菌の影響は、歯周病だけでなく、むし歯や口臭の面でも注目されています。
善玉菌や悪玉菌などに作用することで口腔環境を整備して、総合的に口腔内の健康維持をサポートするからです。
乳酸菌とむし歯菌
ミュータンス菌は、糖分をエサにして強い酸を産生し、歯のエナメル質を溶かすことで、むし歯の原因になります。一方、口腔内で活動する特定の乳酸菌は、アルカリ性物質を産生し、この酸を中和することで、むし歯菌が好む強い酸性環境を作りにくくすると考えられています。また、乳酸菌が糖を先に利用することで、口腔内バランスの維持に寄与する可能性も指摘されています。
※乳酸菌は乳酸などの有機酸を出して口腔内を酸性化することがありますが、これはpHを軽く下げる弱酸性化で、むし歯菌ほどの強酸にはなりません。
また、乳酸菌は口腔内において歯垢が付着しにくくなるような働きを持つ種類もあり、むし歯菌が定着しやすい環境を変える一助になるとされています。
口臭の原因となる悪玉菌と口腔環境
口臭の主な原因とされるのは、酸素が少ない場所で活動する悪玉菌が産生する硫黄化合物です。
乳酸菌の中には、口腔内を弱酸性に保つことで悪玉菌が増えにくい環境づくりに関わるものや、悪臭物質の産生に関与する菌に対して影響を及ぼす可能性があるものも報告されています。
ただし、乳酸菌の働きには個人差があり、継続的に摂取することで安定的に作用が現れると言われています。また、胃腸の不調や糖尿病、ストレス由来の口臭には、別の対応が必要になる場合もあります。
とはいえ、乳酸菌を日々取り入れることは、健やかな口腔環境を保ちやすくする習慣として、注目されています。
口腔内環境をサポートする乳酸菌は?
ここからは、歯科医師の間でも口腔内の健康維持に役立つ可能性があるとして注目されている乳酸菌を紹介します。
L8020乳酸菌の口腔ケア効果とは
L8020乳酸菌は、ラクトバチルス・ラムノーサスL8020株と言って、むし歯や歯周病のない健康な人の口腔内から発見された乳酸菌です。
この乳酸菌は、歯周病やむし歯の原因とされる菌に対して作用することが報告されており、口腔内環境の維持に関連する研究が進められています。
L8020乳酸菌の特徴は、口の中に定着しやすく、他の常在菌のバランスを乱しにくいことです。また、胃酸や胆汁に強いため、腸まで届きやすく、長期的な摂取によるサポートが期待されています。
その他の乳酸菌
L8020以外にも、口腔内環境を整えることが期待できる乳酸菌の種類があります。ラクトバチルス・ロイテリ菌は、人の母乳にも含まれている乳酸菌です。殺菌物質であるロイテリンを分泌して、歯周病の原因菌に働きかける可能性があると考えられています。
ビフィズス菌の一部の株も、口腔内の悪玉菌が増えにくい環境を整えるとされるものもあります。酢酸などの酸を作って口腔内のpHを下げ、悪玉菌が生きづらい環境作りをサポートします。
これらの菌は体内にもともと存在する菌と親和性が高いとされています。特に、人の母乳由来の乳酸菌は、赤ちゃんの口腔内環境を整える自然な働きが期待されています。大人の口腔ケアにおいても、この自然な働きが活用できるとして、安全性が高い種類として注目されています。
乳酸菌はそれぞれ異なる特徴を持っているため、歯科医師と相談しながら、自分に合った種類を確認し、選択することが大切です。
EF2001(Enterococcus faecalis EF-2001)について
1. カンジダ菌の抑制
鶴見大学歯学部との共同研究により、EF2001が**口腔内のカンジダ菌(Candida albicans)**の増殖を有意に抑制することが確認されました 。
臨床試験では、40〜80歳の被験者12名中92%でカンジダ菌の減少が見られました。
2. 口腔カンジダ症の改善
EF2001を含むサプリメントを1週間摂取した結果、**口腔内の不快症状(乾燥、口臭、ネバつきなど)**が改善されたという報告があります 。
3. 口腔内細菌叢のバランス調整
善玉菌と悪玉菌のバランスを整えることで、口腔内の健康維持や全身の健康にも寄与する可能性があるとされています 。
研究とエビデンス
EF2001の口腔ケア効果は、国際学術誌「Beneficial Microbes」にも掲載されており、科学的な裏付けがあります 。
口腔内の細菌バランスが腸内環境や全身の免疫にも影響を与える「腸-口腔相関」の観点からも注目されています。
まとめ
EF2001は、単なる整腸作用にとどまらず、口腔内の悪玉菌抑制や口腔カンジダ症の予防・改善にも効果が期待される乳酸菌です。特に高齢者や免疫力が低下している方にとって、口腔ケアと全身の健康維持を両立できるサポート成分として注目されています。
オススメ乳酸菌摂取方法と日常ケア
乳酸菌は、口腔内の健康維持のために役立ちますが、一時的な摂取では良い効果は期待できません。また、正しい摂取方法や摂取するタイミングも大きなポイントです。
継続的な摂取ができるように、日々のケアに乳酸菌を取り入れることで、健康で衛生的な口腔環境を保ちやすくなります。
ヨーグルトとタブレットの効果的な摂取方法
ヨーグルトは、最も普及している乳酸菌製品の一つです。毎日食べることで、口腔内の善玉菌の増加とバランス維持が可能になります。
これらを選ぶ時は、目的に応じて選ぶのがポイント。口臭や歯周病対策としては、L8020やL.ロイテリ菌を含む製品がおすすめです。砂糖が加えられていない製品を選び、1日100〜200gの摂取を目指しましょう。
一方、タブレットは「口の中でゆっくり溶かすタイプ」を選ぶことで、口腔内に乳酸菌が留まりやすくなり、より高い効果が期待できます。就寝前や食後の摂取を心がけましょう。
歯磨きと組み合わせた口腔ケアの最適化
乳酸菌の効果を最大限に活かすためには、歯磨きや舌の清掃などの基本的な口腔ケアを丁寧に行うことが大切です。特に、就寝前にしっかり歯磨きをして虫歯菌や歯周病菌のもととなる汚れを取り除き、口腔内を清潔にすることで、乳酸菌が留まりやすくなり、善玉菌の定着が促進されます。歯磨きで悪玉菌を除去した後に乳酸菌を摂取することを心がけましょう。
ただし、フッ素入り歯磨き粉を使用する場合は30分~1時間程度あけてからの摂取が良いでしょう。一部の乳酸菌はフッ素の残留によって活性が減少することがあるため、口の中への乳酸菌の定着に影響が出ることがあります。
摂取タイミングと継続のポイント
乳酸菌を摂取するタイミングは、就寝前がおすすめです。口内が清潔になった後に乳酸菌を摂取することで、清浄な口腔環境の中で、乳酸菌が働きやすくなります。
また、乳酸菌は「一時的に留まる菌」が多いため、毎日続けることが効果を実感するためのカギとなります。朝食時や夜の歯磨き後など、毎日同じ時間、習慣化しやすい時間に摂取することで、継続しやすくなるでしょう。食後30分以内、または就寝前に決まった時間に摂取するのがおすすめです。
効果を実感するまでには2〜4週間かかります。途中で断念することなく継続することも大きなポイントです。
サプリメントで簡単に
歯周病と乳酸菌の関係性【むし歯や口臭】口腔環境のサポートによる効果とは?のまとめ
歯周病が気になる方にとって、毎日の歯磨きや定期的な歯科検診はもちろん大切です。それに加えて、乳酸菌の摂取は、歯医者にも注目されている日常的な口腔ケアの補助になります。
乳酸菌入りのヨーグルトやタブレットを日常の口腔ケアに意識して取り入れ、継続的に摂取することで、より健やかな口腔環境を目指せるでしょう。
※既に歯周病が進行している場合は、乳酸菌摂取だけでなく専門的な治療が必要です。お口の健康に関するご相談や定期検診の予約については、かかりつけの歯科医院にお気軽にお問い合わせください。乳酸菌を活用した口腔ケアで、健康な歯と歯茎を維持しましょう。
※本記事の内容は研究報告に基づく情報提供を目的としており、特定の効果を保証するものではありません。口腔内の健康状態には個人差があります。気になる症状がある場合は、歯科医師にご相談ください。

